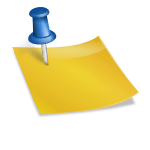2025年10月15日、ローソンが発表した決算は過去最高益という明るいニュースだった。しかし、その陰で100円業態の「ローソンストア100」は最盛期の半分以下となる621店舗にまで減少し、月2-3店舗ペースで閉店が続いている。リーマンショック後の節約ブームで急拡大した「コンビニ×スーパー×100円ショップ」の融合業態は、なぜ苦戦を強いられているのか。ドラッグストアやディスカウントストアなど競合の台頭、100円ショップ業態の一般化という市場環境の激変を背景に、その真相を探る。
ローソンストア100の現状:621店舗まで減少、止まらない閉店の連鎖
2025年10月15日、ローソンが発表した2025年3-8月期の決算内容は、小売業界に明暗を分ける象徴的な数字となった。親会社であるローソン全体の純利益は383億円と前年同期比10%増を記録し、過去最高益を更新。国内のコンビニエンスストア事業が好調で、客単価の上昇や新商品の投入が功を奏している。
しかし、その成功の裏側で、100円業態を軸とした「ローソンストア100」は深刻な苦境に立たされている。2025年9月末時点での店舗数は621店舗。最盛期には1200店舗以上を展開していたことを考えると、実に半分以下にまで減少したことになる。さらに注目すべきは、この半年間だけで16店舗が閉店し、月平均2-3店舗という閉店ペースが続いていることだ。
関連記事
業績指標も厳しい現実を物語る。2025年9月の売上高は前年同月比95.5%、客数は92.3%と、いずれも前年を下回った。唯一、客単価だけが100%を超えているが、これは商品の値上げによる要因が大きく、実質的な顧客離れが進んでいることを示唆している。
かつて「コンビニの利便性」「スーパーの品揃え」「100円ショップの価格」という三位一体の強みで消費者の支持を集めたローソンストア100。リーマンショック後の節約ブームを追い風に急成長を遂げた同業態が、なぜここまで苦戦しているのか。その背景には、小売業界全体を揺るがす大きな構造変化が隠されている。
好調なローソン本体との対比が際立つ業績格差
2025年10月15日に発表されたローソンの決算内容は、小売業界に大きな衝撃を与えた。2025年3-8月期の連結純利益は383億円と、前年同期比で10%増という力強い成長を見せ、過去最高益を更新したのだ。この好調の原動力は、国内のコンビニエンスストア事業にある。新商品の開発力、デジタル戦略の推進、そして何より「利便性」という本質的価値の追求が、消費者の支持を集めている。
しかし、同じローソングループの一員でありながら、ローソンストア100の業績は対照的だ。2025年3月末には637店舗あった店舗数が、わずか半年後の9月末には621店舗にまで減少。16店舗が閉店したことになる。単純計算で月平均2-3店舗という閉店ペースは、業態そのものの存続に関わる深刻な水準だ。
さらに注目すべきは、売上高と客数の前年割れだ。2025年9月の売上高は前年同月比95.5%、客数は92.3%と、いずれも90%台に落ち込んでいる。一方で客単価は100%を超えているが、これは商品の値上げによる影響が大きい。つまり、客数が減少しているにもかかわらず、値上げで単価を維持しているという構図だ。この状況が続けば、さらなる客離れを招く悪循環に陥る可能性が高い。
ローソン本体が過去最高益を更新する一方で、ローソンストア100が苦戦している。この対比は、単なる業績の良し悪しではなく、小売業界における「勝ち組」と「負け組」の分水嶺を象徴している。コンビニとしての利便性を極めたローソン本体と、業態の独自性を失いつつあるローソンストア100。この差は、今後さらに広がる可能性がある。
最盛期1200店舗から621店舗へ:閉店ラッシュの実態
ローソンストア100の店舗数推移を見ると、その凋落ぶりが鮮明になる。最盛期である2008年から2010年頃には1200店舗以上を展開していたが、2025年9月末時点では621店舗にまで減少。実に半分以下の水準だ。この15年間で約600店舗が閉店したことになる。
特に注目すべきは、直近半年間の閉店ペースだ。2025年3月末の637店舗から9月末の621店舗へと、わずか半年で16店舗が閉店している。月平均2-3店舗という閉店ペースは、年間に換算すると30店舗以上にもなる。このペースが続けば、2030年には500店舗を割り込む可能性すらある。
閉店の背景には、収益性の悪化がある。売上高と客数が前年割れを続ける中、固定費である家賃や人件費は上昇傾向にある。特に都市部の店舗では、家賃負担が重くのしかかる。さらに、商品の値上げによる客離れが加速すれば、採算ラインを下回る店舗が増加し、閉店せざるを得ない状況に追い込まれる。
また、エンタナビの報道によれば、「ある店舗」の影響で業績が悪化しているという。この「ある店舗」とは、ドラッグストアやディスカウントストアを指していると推測される。近年、ドラッグストアは生鮮食品の取り扱いを強化し、100円ショップ的な低価格商品も充実させている。ディスカウントストアも同様に、食品から日用品まで幅広く低価格で提供している。これらの競合店舗が、ローソンストア100の顧客を奪っているのだ。
「99エンオンリーストア」から「ローソンストア100」への歴史的変遷
ローソンストア100の起源は、1996年に遡る。株式会社ベストが「99エンオンリーストア」として開業したのが始まりだ。当時、100円ショップ業態は珍しく、「99円で何でも買える」というコンセプトは消費者に新鮮な驚きを与えた。2001年には株式会社九九プラスに改名し、「SHOP99」としてブランドを確立。コンビニとスーパーの中間的な業態として、徐々に支持を広げていった。
大きな転機となったのは、2007年のローソンとの業務・資本提携、そして2008年のローソン連結子会社化だ。この時期は、リーマンショックが世界経済を揺るがした時期と重なる。景気後退による節約志向の高まりが、100円業態に追い風となった。「コンビニの利便性」「スーパーの品揃え」「100円ショップの価格」という三位一体の強みが、節約を求める消費者のニーズに完璧にマッチしたのだ。
2011年には、全店舗が「ローソンストア100」に統一された。ローソンブランドの信頼性と、100円業態の価格訴求力を融合させた新業態として、急速に店舗数を拡大。最盛期には1200店舗以上を展開し、小売業界の成功モデルとして注目を集めた。肉・野菜などの生鮮食品から、生活用品まで幅広く取り揃え、「だけ弁当」などのユニークな商品も話題となった。
しかし、リーマンショック後の節約ブームが一段落すると、状況は一変する。ドラッグストアやディスカウントストアといった競合が台頭し、100円ショップ業態も一般化。ローソンストア100の独自性は薄れていった。さらに、商品の値上げによる100円業態からの脱却も、顧客離れを加速させた。こうして、かつての成功モデルは、苦戦を強いられる存在へと変貌していったのだ。
親会社ローソンの戦略における位置づけの変化
ローソンストア100が苦戦する一方で、親会社ローソンの戦略における位置づけも変化している。かつて、ローソンストア100はローソンの多様性を象徴する存在だった。通常のコンビニでは取り込めない、価格志向の顧客層をターゲットとする重要な業態として期待されていた。しかし、業績悪化が続く現在、その戦略的意義は薄れつつある。
ローソン本体は、デジタル戦略やプライベートブランドの強化、健康志向商品の開発など、コンビニとしての本質的価値を高める方向に舵を切っている。一方、ローソンストア100は、業態の独自性を失いつつあり、通常のコンビニやスーパーとの差別化が難しくなっている。親会社としては、投資対効果を考えると、ローソン本体への資源集中が合理的な判断となる。
実際、ローソンストア100への新規出店はほぼ停止状態にある。代わりに、収益性の低い店舗を順次閉店し、店舗網を最適化する戦略が取られている。この流れは、今後も続く可能性が高い。ローソンストア100という業態そのものの将来性が、問われているのだ。
「コンビニ×スーパー×100円ショップ」融合業態の独自性
ローソンストア100の最大の特徴は、「コンビニ」「スーパーマーケット」「100円ショップ」という三つの業態を融合させた点にある。コンビニの利便性である24時間営業や駅近立地、スーパーの豊富な品揃えである生鮮食品や日配品、そして100円ショップの圧倒的な価格訴求力。これらを一つの店舗で実現することで、他にはない独自のポジションを築いた。
特に注目されたのは、生鮮食品の取り扱いだ。通常のコンビニでは取り扱いが少ない肉や野菜を、100円前後の低価格で提供。一人暮らしの若者や高齢者にとって、少量を低価格で購入できるのは大きな魅力だった。また、調理済みの惣菜や弁当も充実しており、「ちょっとした買い物」に最適な店舗として支持を集めた。
しかし、この独自性は時間とともに色褪せていった。ドラッグストアが生鮮食品の取り扱いを始め、ディスカウントストアが低価格商品を充実させる中で、ローソンストア100の差別化要因は薄れていった。さらに、100円という価格設定も、インフレ環境下では維持が困難となり、値上げせざるを得なくなった。結果として、「100円ショップ」としてのアイデンティティも曖昧になってしまったのだ。
「だけ弁当」に象徴されるヒット商品の功績と限界
ローソンストア100を語る上で欠かせないのが、「だけ弁当」だ。この商品は、おかずが1種類だけという極めてシンプルな構成でありながら、100円という低価格と、「唐揚げだけ」「ハンバーグだけ」といった潔さが消費者の心を掴んだ。SNSでも話題となり、ローソンストア100の代名詞的存在となった。
「だけ弁当」の成功は、ローソンストア100の商品開発力の高さを示すものだった。既存のコンビニ弁当とは一線を画す、ユニークなコンセプトと低価格の両立。これは、100円業態ならではの強みと言えた。しかし、この成功は同時に、業態の限界も浮き彫りにした。「だけ弁当」のような特定商品の人気だけでは、店舗全体の業績を支えることはできなかったのだ。
さらに、値上げの波は「だけ弁当」にも及んだ。当初100円だった商品が、インフレの影響で値上げされると、消費者の反応は厳しかった。100円という価格設定が、商品の価値そのものを形成していたため、値上げは単なる価格変更ではなく、商品のアイデンティティを揺るがす事態となった。ヒット商品であっても、環境変化には抗えなかったのだ。
100円業態の一般化と差別化困難という市場環境の激変
ローソンストア100が登場した1990年代後半から2000年代初頭、100円ショップ業態はまだ珍しかった。ダイソーやセリアといった専門店が台頭し始めた時期ではあったが、食品を含む幅広い商品を100円で提供する業態は、革新的だった。しかし、2020年代に入ると、状況は一変する。100円ショップは全国に広がり、もはや特別な存在ではなくなった。
さらに深刻なのは、他業態による侵食だ。ドラッグストアは、医薬品だけでなく、食品や日用品の取り扱いを大幅に拡大。生鮮食品まで扱う店舗も増えている。しかも、ローソンストア100と同等かそれ以上の低価格で提供しているケースも少なくない。ディスカウントストアも、業務スーパーやオーケーストアのように、圧倒的な低価格で消費者を引きつけている。
こうした競合の台頭により、ローソンストア100の独自性は急速に失われていった。「コンビニ×スーパー×100円ショップ」という融合業態は、かつては画期的だったが、今では多くの店舗が似たようなコンセプトを採用している。差別化が困難になった結果、消費者は単純に「より安い店」「より便利な店」を選ぶようになり、ローソンストア100の優位性は消失してしまったのだ。
店舗の現場から見える「静かな撤退」の実態
平日の午後3時、東京都内のある住宅街にあるローソンストア100を訪れた。店内に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、やや古びた内装だ。通常のローソンが次々とリニューアルされ、明るく清潔感のある店内に生まれ変わっているのとは対照的に、ローソンストア100の店舗は2010年代初頭の雰囲気をそのまま残している。蛍光灯の光は少し黄ばみがかり、床のタイルには経年劣化の跡が見える。
商品棚を見渡すと、かつての「100円均一」の名残が随所に感じられる。「だけ弁当」のコーナーには、唐揚げだけ、ハンバーグだけ、という潔いラインナップが並んでいる。ただし、価格は100円ではなく、130円や150円に値上げされている。消費者の反応は、控えめに言っても厳しい。店内には数人の客がいたが、手に取っては戻し、また別の商品を手に取るという動作を繰り返している。
生鮮食品コーナーに目を向けると、野菜や果物が並んでいる。キャベツ1/4カット、玉ねぎ2個、バナナ3本など、一人暮らし向けの少量パックが中心だ。ただし、新鮮さには疑問符がつく。野菜の葉先がやや萎れており、果物も完熟を過ぎた印象だ。近隣のドラッグストアやスーパーと比較すると、品質面での差は歴然としている。価格も、かつてのような圧倒的な安さはなく、むしろドラッグストアの方が安い商品も少なくない。
レジで会計を待つ間、店員の疲弊した表情が目に入る。人手不足は深刻で、一人の店員がレジと品出しを兼任している。客が増えると、すぐにレジ待ちの列ができる。こうした状況は、通常のローソンでは見られない光景だ。人件費を抑えるために最低限の人員で回しているのだろうが、それがサービス品質の低下を招き、さらなる客離れにつながるという悪循環に陥っている。
店を出て、近隣の商業施設を歩いてみる。徒歩5分圏内には、大手ドラッグストアが2店舗、ディスカウントストアが1店舗ある。ドラッグストアに入ると、ローソンストア100よりも広い売り場に、充実した食品コーナーが展開されている。生鮮食品はもちろん、冷凍食品や日配品も豊富だ。しかも、価格はローソンストア100と同等かそれ以下。ポイントカードやアプリのクーポンも充実しており、実質的な価格はさらに安くなる。
ディスカウントストアも同様だ。業務用サイズの商品が並ぶ中、一人暮らし向けの少量パックも充実している。しかも、品質は高く、価格は圧倒的に安い。レジの効率も良く、待ち時間はほとんどない。こうした競合店舗と比較すると、ローソンストア100の劣勢は明らかだ。「コンビニの利便性」「スーパーの品揃え」「100円ショップの価格」という三位一体の強みは、もはや過去のものとなっている。
夕方、再び別のローソンストア100を訪れた。ここは駅前の好立地にある店舗だが、客足はまばらだ。通勤客が次々と通り過ぎていくが、立ち寄る人は少ない。隣には通常のローソンがあり、そちらには多くの客が入っていく。同じローソングループでありながら、この差は何を意味するのか。通常のローソンは、コンビニとしての本質的価値である「利便性」を追求し、品質の高い商品とサービスを提供している。一方、ローソンストア100は、かつての独自性を失い、中途半端な存在となってしまっている。
📊 ローソンストア100の拡大から縮小への時系列フロー
❓ よくある質問(FAQ)
Q1: ローソンストア100が閉店ラッシュになっている主な理由は?
A: 主な理由は3つあります。①ドラッグストアやディスカウントストアなど競合の台頭により、独自性が失われたこと。②インフレによる値上げで、100円業態としてのアイデンティティが曖昧になり、客離れが加速したこと。③100円ショップ業態そのものが一般化し、差別化が困難になったこと。これらが複合的に作用し、売上高と客数の前年割れが続いています。
Q2: ローソン全体は好調なのに、なぜローソンストア100だけが苦戦しているのですか?
A: ローソン本体は、コンビニとしての本質的価値である「利便性」を追求し、デジタル戦略やプライベートブランドの強化、健康志向商品の開発などで差別化に成功しています。一方、ローソンストア100は、「コンビニ×スーパー×100円ショップ」という融合業態の独自性が薄れ、通常のコンビニやスーパーとの差別化が困難になっています。親会社の戦略も、ローソン本体への資源集中に傾いており、ローソンストア100への投資は縮小傾向です。
Q3: 「だけ弁当」などのヒット商品があるのに、なぜ業績が悪化しているのですか?
A: 「だけ弁当」は確かにヒット商品ですが、特定商品の人気だけでは店舗全体の業績を支えることはできません。さらに、インフレの影響で「だけ弁当」も値上げされたため、当初の100円という価格設定が持つ魅力が失われました。100円という価格が商品の価値そのものを形成していたため、値上げは単なる価格変更ではなく、商品のアイデンティティを揺るがす事態となりました。
Q4: ローソンストア100は今後、完全に消滅する可能性がありますか?
A: 完全消滅は断言できませんが、現在の閉店ペースが続けば、店舗数はさらに減少する可能性が高いです。親会社ローソンとしては、収益性の低い店舗を順次閉店し、店舗網を最適化する戦略を取っています。一方で、業態そのものの抜本的な見直しや、新たな差別化戦略が打ち出されなければ、縮小は続くでしょう。ただし、特定地域や顧客層に特化した形で存続する可能性もあります。
Q5: ドラッグストアやディスカウントストアとの競争に勝つために、ローソンストア100ができることはありますか?
A: 競争に勝つためには、抜本的な差別化戦略が必要です。例えば、①生鮮食品の品質向上と鮮度管理の徹底、②ローソン本体との連携強化によるプライベートブランドの充実、③デジタル戦略の導入(アプリ、ポイントカード、配達サービス等)、④地域密着型の商品開発(地元食材の活用、高齢者向け商品等)などが考えられます。ただし、これらの戦略にはコストがかかり、親会社の投資意欲次第という面もあります。
Q6: リーマンショック後に急拡大したのに、なぜ今は縮小しているのですか?
A: リーマンショック後は、景気後退による節約志向の高まりが、100円業態に追い風となりました。しかし、その後の景気回復とともに、節約志向は一段落。同時に、ドラッグストアやディスカウントストアといった競合が台頭し、100円ショップ業態も一般化しました。さらに、近年のインフレによる値上げが客離れを加速させ、かつての独自性は完全に失われてしまいました。市場環境の激変に対応できなかったことが、縮小の主因です。
100円業態の栄枯盛衰が示す小売業の本質
ローソンストア100の閉店ラッシュは、単なる一企業の業績悪化ではなく、小売業界全体の構造変化を象徴する出来事だ。リーマンショック後の節約ブームという追い風に乗って急拡大した100円業態は、かつて画期的なビジネスモデルとして注目を集めた。「コンビニの利便性」「スーパーの品揃え」「100円ショップの価格」という三位一体の強みは、消費者のニーズに完璧にマッチしているように見えた。
しかし、市場環境は容赦なく変化した。ドラッグストアは生鮮食品まで取り扱いを拡大し、ディスカウントストアは圧倒的な低価格で消費者を引きつけた。100円ショップ業態そのものも一般化し、もはや特別な存在ではなくなった。こうした競合の台頭により、ローソンストア100の独自性は急速に色褪せていった。かつての成功モデルは、環境変化に対応できず、苦戦を強いられる存在へと変貌した。
さらに深刻なのは、インフレによる値上げだ。100円という価格設定は、単なる数字ではなく、業態のアイデンティティそのものだった。それが値上げによって崩れた時、消費者は「100円ショップではなくなった」と感じた。客単価は100%を超えたが、それは客数の減少を補うための苦肉の策に過ぎない。値上げが客離れを招き、さらなる値上げが必要になるという悪循環に陥っている。
一方で、親会社ローソンは過去最高益を更新している。この対比は、小売業における「勝ち組」と「負け組」の分水嶺を鮮明に示している。ローソン本体は、コンビニとしての本質的価値である「利便性」を追求し続けた。新商品の開発、デジタル戦略の推進、プライベートブランドの強化。こうした取り組みによって、差別化に成功し、消費者の支持を維持している。一方、ローソンストア100は、かつての独自性に固執し、環境変化に対応できなかった。
ローソンストア100の閉店ラッシュから学ぶべき教訓は何か。それは、「差別化」の本質だ。一時的なブームや環境変化に依存した差別化は、長続きしない。本質的な価値を提供し続けること、そして環境変化に柔軟に対応し続けることが、小売業の生命線なのだ。ローソンストア100は、かつての成功に安住し、変化への対応を怠った。その結果が、今の苦境につながっている。
小売業界は、今後さらなる変化にさらされるだろう。デジタル化の進展、消費者ニーズの多様化、労働力不足、環境問題への対応。こうした課題に対して、本質的な価値を見失わず、柔軟に対応できる企業だけが生き残る。ローソンストア100の閉店ラッシュは、その厳しい現実を突きつけている。100円業態の栄枯盛衰は、小売業の本質を問い直す契機となるはずだ。変化に対応できない者は淘汰され、本質を追求する者だけが未来を切り拓く。この普遍的な真理を、私たちは改めて胸に刻むべきだろう。