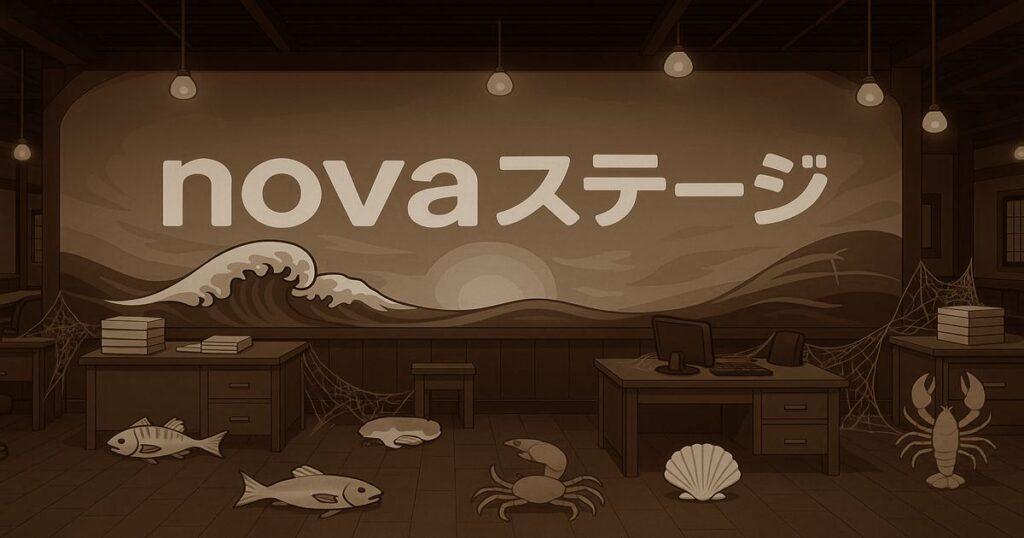「弁当を使う」という表現は、現代の日本語ではほとんど使われることがないものの、過去には「弁当を食べる」という意味で広く使用されていた表現です。
この表現について、さらに詳しく3つの場面に分けて解説し、その背景や現代における認知度、またその文化的な位置づけを考察します。
弁当を使うという言葉はいつの時代に使われた?
「弁当」という言葉の使用は江戸時代初期にさかのぼります。
江戸時代初期(1600年代初頭)に編纂された『日葡辞書』に「Bento(ベンタウ 便当・弁当)」という記載があります。
この辞書は、日本語とポルトガル語の対訳辞書であり、当時すでに「弁当」という言葉が使われていたことを示しています。
『日葡辞書』での「弁当」の説明は、「引出しつきの文具箱に似た箱で、中に食物をいれて携行するもの」とされています。
「弁当」という言葉の起源については、いくつかの説が存在します。一つ目は、戦国時代に「配当を弁ずる」または「当座を弁ずる」という言い回しから派生したという説です。
二つ目は、安土桃山時代(織田信長や豊臣秀吉の時代)に成立したという説です。
三つ目は、中国南宋時代の俗語「便當」(好都合、便利なこと)を語源としているという説です。
いずれの説にしても、「弁当」という言葉が一般的に使用され始めたのは江戸時代初期であり、それ以降、携行する食べ物を指す言葉として定着したと考えられます。
意味と使用状況

「弁当を使う」という表現は、文字通り「弁当を食べる」という意味を持ちますが、現代の日本語ではほとんど使われることがなく、特に日常的な会話ではほぼ聞くことはありません。
この表現は、文学作品や古典的な文章の中で見られるもので、特に江戸時代から明治時代にかけて使われていたとされています。
たとえば、作家中勘助の小説『銀の匙』にもこの表現が登場し、当時の言葉遣いとして知られています。
このように、「弁当を使う」という表現は、ただの食事を指すだけでなく、その時代の社会的な背景や文化を色濃く反映した言い回しの一つと考えられます。
現代では「弁当を食べる」が一般的ですが、「弁当を使う」という表現は、少し格式があり、古風で硬い印象を与えます。
このような言い回しは、日常生活で使用するにはやや不自然に感じられるため、文学的な文脈や時代背景を考慮しながら使われることが多いです。
また、日常会話において「弁当を使う」というフレーズが使われるとすれば、「早めに弁当を使う」という形になりますが、この場合も「早めに弁当を食べる」と同じ意味を持ちます。
つまり、文脈によっては、急いで弁当を食べるというニュアンスが含まれることもあります。
このように、かつて使われたこの表現は、現代の日本語ではすっかり廃れてしまったものの、特定の文脈で使われると、時代背景を理解している人々には懐かしく響くこともあります。
現代における認知度
「弁当を使う」という表現は、現代ではほとんど使われることがないため、若い世代を中心にあまり知られていないことが多いです。
この言い回しを聞いたことがない、あるいは意味がわからないという人が多いでしょう。現代の日本語では、「弁当を食べる」という言い方が圧倒的に一般的であり、こちらの表現の方が広く受け入れられています。
例えば、若い世代が「弁当を使う」という表現を聞いた場合、その意味がすぐに理解できない可能性が高いです。
そのため、現代の会話においては「弁当を使う」という言い回しを使うことは避けられ、代わりに「弁当を食べる」を用いる方が通じやすく、自然です。
また、「弁当を使う」という表現が死語に近い状態になった背景には、言語の進化とともに言葉が変化し、古い表現が次第に使われなくなったことが挙げられます。
特に若い世代が使わない表現であるため、この言い回しが日常的に通じる場面はほとんどありません。
とはいえ、文学や古典作品を愛する人々にとっては、あくまでその背景にある時代の文化や社会を理解する上で重要な言葉となっています。
現代日本語の使用においては、もはや珍しい表現であるものの、過去の言語や文化を学ぶ上では興味深い存在であり、文学作品や古典的な文脈で目にすることができるかもしれません。
文化的背景と結論
「弁当を使う」という表現は、江戸時代やその前後の時代の日本語における特有の言い回しの一つです。
この表現は、当時の職人や商人、さらには江戸っ子と呼ばれる人々の間で用いられていた言葉で、威勢の良い言い回しが特徴でした。
江戸時代の日本では、食事に関する言葉遣いが非常に特徴的であり、食べ物を「使う」と表現することで、食事を早急に済ませるといったニュアンスが込められていました。
また、この言葉はその時代の庶民文化や、職人たちの簡潔で力強い言葉使いを反映していると言えるでしょう。
しかし、現代においてこの表現はほとんど使用されていないため、若い世代には全く認識されないことが多く、その意味や背景を理解することは一部の人々に限られています。
このように、「弁当を使う」という表現は、今日ではほとんど死語として扱われている一方で、過去の日本語や文化を学ぶ際には興味深い事例となり、古典文学や歴史的背景を知る上で欠かせないものとなっています。
結論として、「弁当を使う」という表現は現代においてはほとんど使用されていないものの、特定の文学的文脈や文化的背景において理解される重要な言葉です。
この表現を知ることは、過去の日本語の豊かさや、時代ごとの言語の変遷を学ぶ一助となり、言葉の歴史的変化について深く考えるきっかけとなるでしょう。

まとめ
- 江戸時代初期に登場し、食べる意味で使われていた。
- 起源には戦国時代や南宋の俗語説がある。
- 現代では文学作品でのみ見られる。
- 「弁当を食べる」が一般的な表現。
- 若い世代には意味が理解されない。
- 江戸時代の庶民文化を反映した表現。