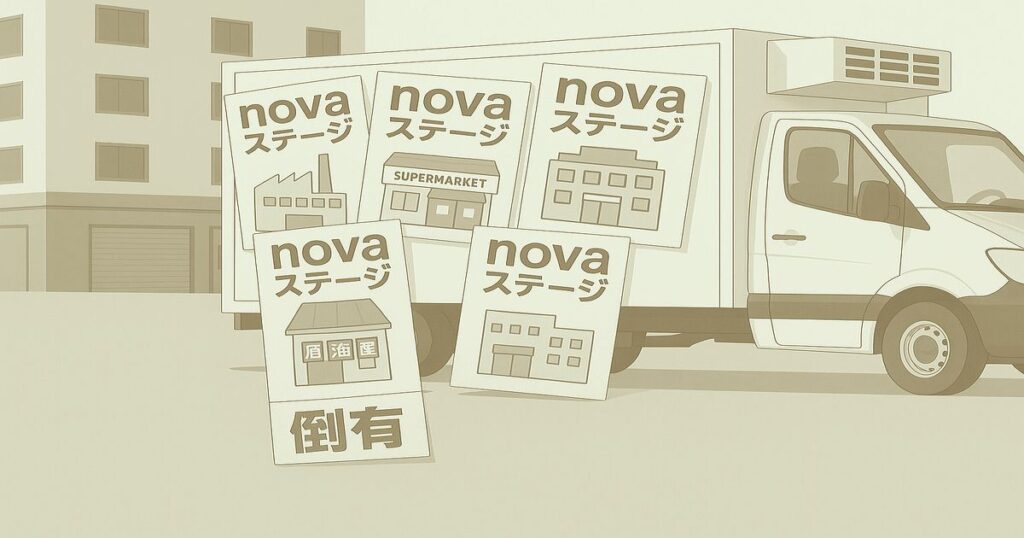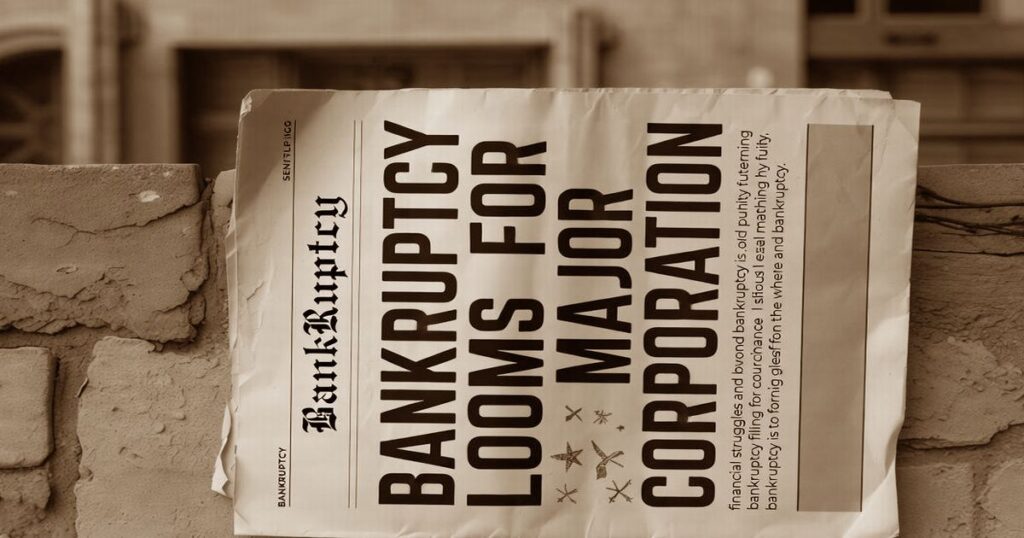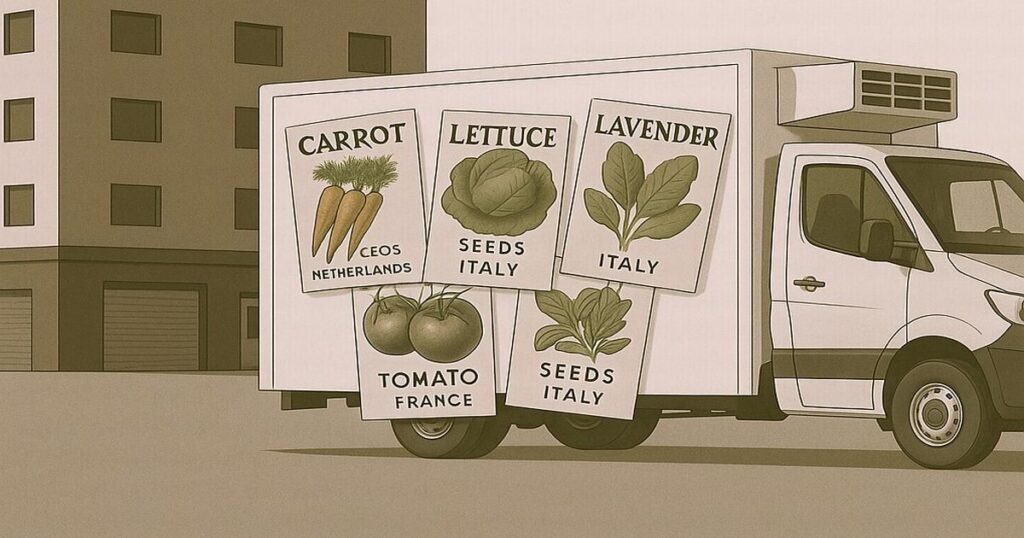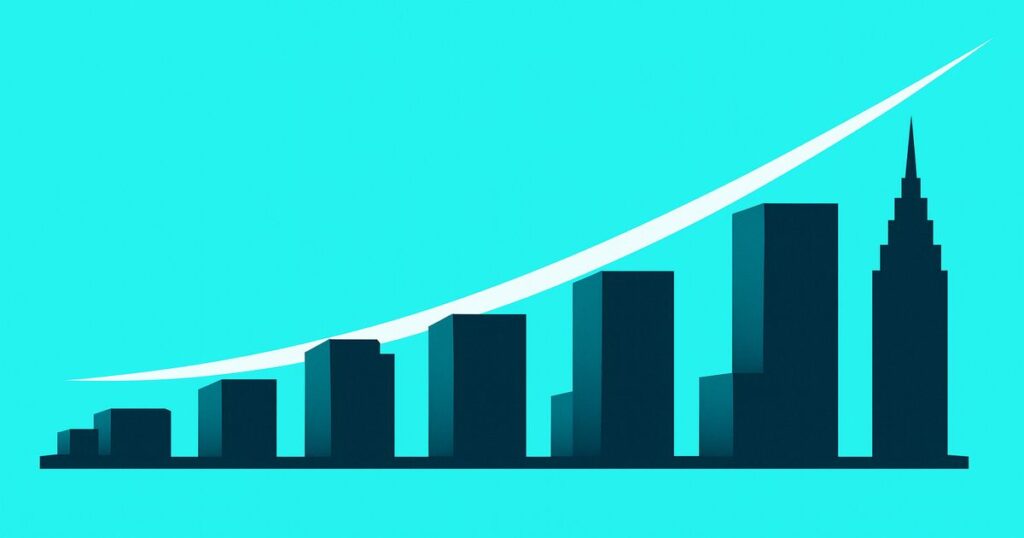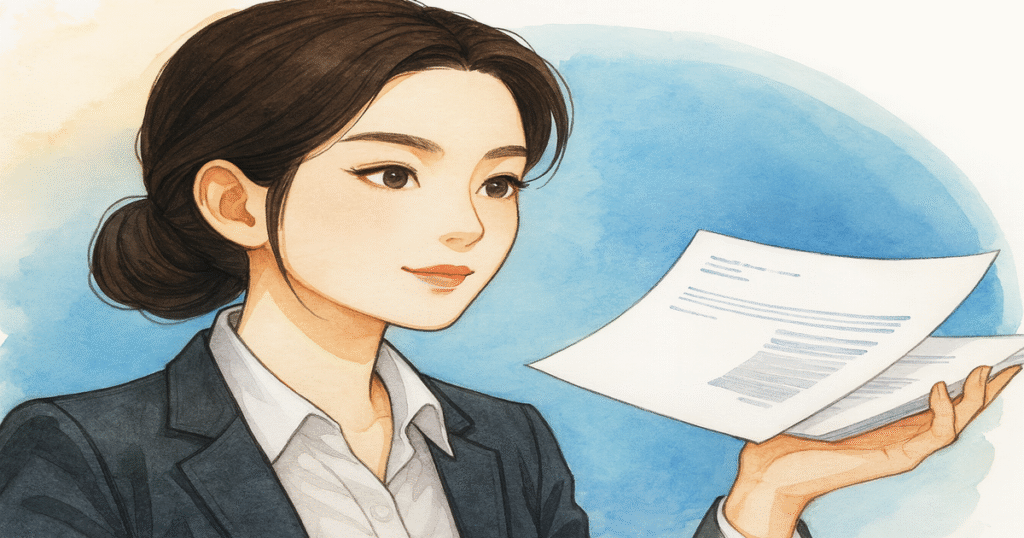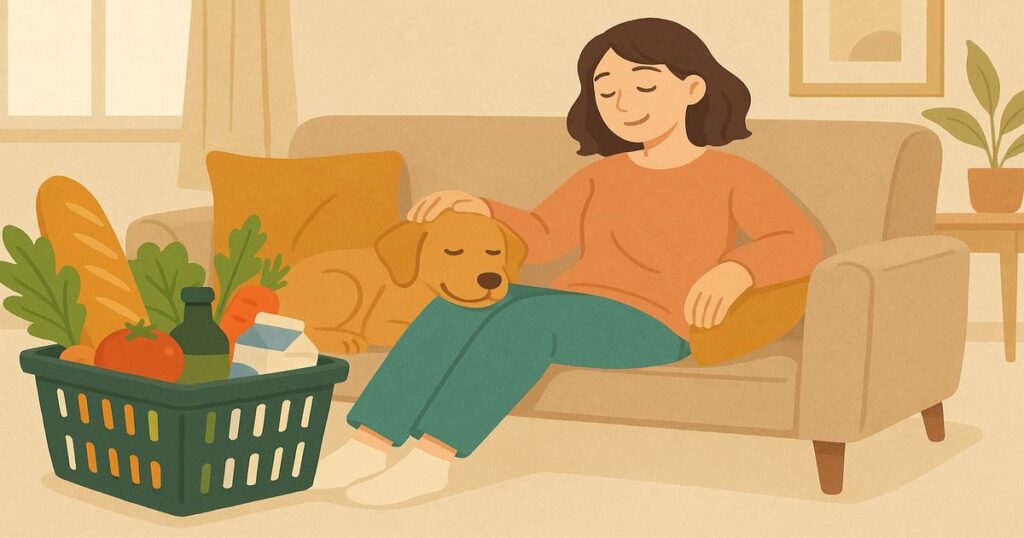-

震災から14年…石巻ヤマボシ渡邊商店はなぜ破産したのか?
-

ルンバの米アイロボット破産申請!中国企業傘下で再建へ
-

㈱アシスト・㈱エヌ・コム特別清算!通信業界の構造変化とは?
-

企業倒産1万件超え確実!中小企業を襲う現実とは
-

売上3億円企業が破産!ガーデンアシストに何が?
-

蕎麦処文ざが破産へ!老舗そば店に何が起きた?
-

松之山温泉・野本旅館が自己破産へ!地方旅館の現実とは?
-

下妻運送が破産手続き開始決定!負債2億円の真相とは?
-

三条プレス工業所が自己破産へ!後継者難と高齢化の現実
-

愛媛「Life with Green」破産の深層事情とは