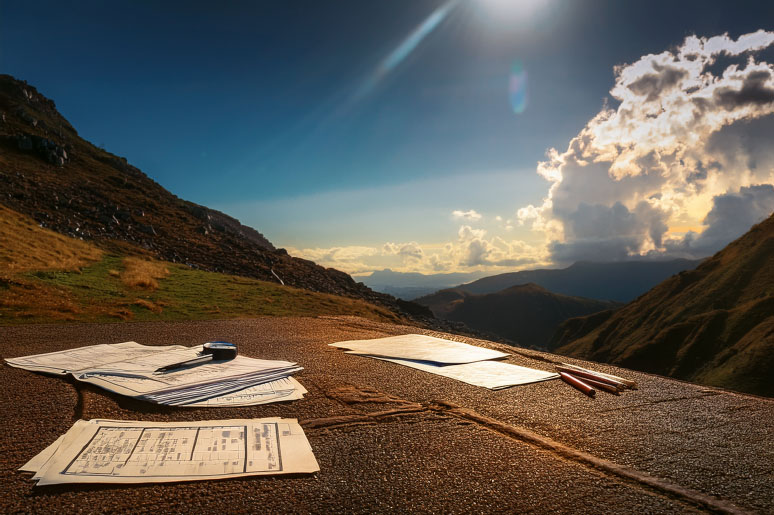英語能力試験の権威を揺るがす不正事件の全容。マスクの下に隠されたマイク、900点超の高得点、そして組織的な関与の疑い。現代社会が抱える「試験依存」という病理の姿とは。
- 替え玉受験
- 信頼低下
初夏の試験会場で発覚したTOEIC替え玉受験事件の全容
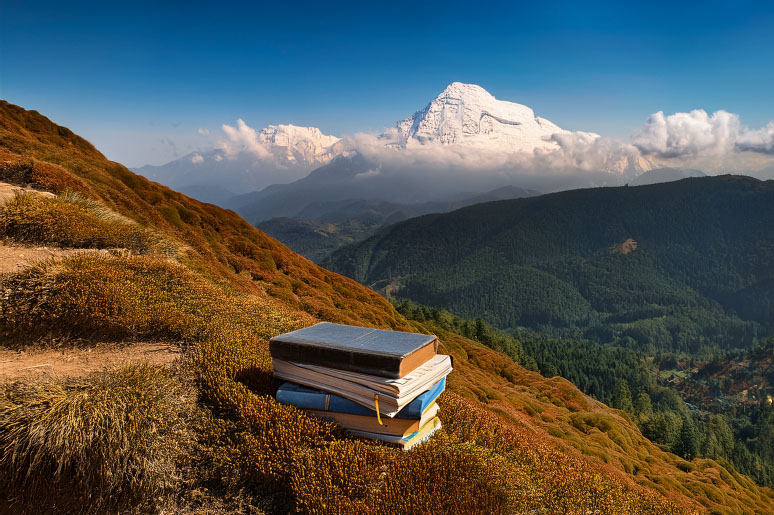
2025年5月18日、東京都板橋区のTOEIC試験会場。新緑の季節を迎えたこの日、一人の大学院生が他人名義の受験票を使って試験会場に侵入しようとしていた。中国籍の京都大学大学院生(27)である。
しかし、彼の行動は試験運営側の警戒網にかかっていた。不審な高得点の報告を受けた試験運営法人からの相談を契機に、警察はすでに警戒態勢を敷いていたのだ。
「容疑者は、自身の顔写真を貼り付けた他人名義の受験票を使用していました。これは昨年6月と今年3月にも同様の手口で受験していた疑いがあります」と捜査関係者は語る。
昨年から続いていたTOEIC替え玉受験の手口
驚くべきことに、王容疑者は過去2回のTOEIC受験で、いずれも990点満点中900点以上という驚異的な高得点を記録していた。
これらの点数は、当然ながら本人の英語力を示すものではなく、他人のキャリアや学歴に利用されていた可能性が高い。
「容疑者のマスク内から発見された小型マイクは、試験中に解答を他の受験者に伝えるための装置だった可能性があります」と捜査関係者は明かす。
わずか3~4センチほどの小型マイクは、現代のテクノロジーを不正に利用した巧妙な手口だった。
「容疑者は『インターネットで仕事に応募し指示を受けた』『報酬を得る約束があった』と供述しています。これは個人的な動機というより、組織的な不正の一環である可能性が高いでしょう」(捜査関係者)
TOEIC試験における替え玉受験の実態と背景

就職・進学を左右するTOEIC点数への依存
TOEICのスコアは、多くの企業や教育機関で採用や入学の判断材料として重視されている。特に900点を超えるスコアは、就職活動や進学において大きなアドバンテージとなる。
「TOEICの点数は、単なる英語力の証明から、キャリア形成のための『必須アイテム』へと変質しています」と語学教育専門家の田中博士(仮名)は指摘する。「この『点数至上主義』が、不正行為を生み出す土壌となっているのです」
試験会場では、当日の受験者の約30%が欠席していたという事実も気になる点だ。この高い欠席率は、不正行為に関与するグループの存在を示唆している可能性もある。
組織的なTOEIC不正受験の疑い
警察の調べによると、王容疑者は「インターネットで仕事に応募し指示を受けた」と供述しているという。これは、いわゆる「替え玉受験請負業」の存在を示唆している。
「中国や韓国など、英語能力試験の重要性が高い国々では、以前から同様の不正行為が問題視されてきました」と国際教育の専門家は語る。「日本でも、留学生を中心に同様の組織が活動している可能性は否定できません」
- 写真:本人の顔写真を受験票に貼り替え
- 身分:他人名義で高得点を取得
- 機器:小型マイクを使った解答の伝達
- 組織:インターネットを通じた請負業の関与
試験制度の脆弱性と社会が抱える本質的問題
本人確認の甘さが露呈したTOEIC試験制度
今回の事件で浮き彫りになったのは、TOEIC試験における本人確認の甘さだ。受験票に貼られた写真との照合のみで、本人確認が行われているという現実がある。
「マスク着用が一般的になった近年、顔写真による本人確認の精度はさらに低下しています」とセキュリティ専門家は指摘する。「生体認証など、より厳格な方法の導入が急務でしょう」
また、試験結果の異常な高得点に対する検証システムも不十分だったことが、今回の事件を通じて明らかになった。
「TOEICは国際的な信頼性を保つためにも、不正防止のシステムを早急に見直す必要があります。顔認証技術の導入や、試験形式の多様化を検討すべき時期に来ています」
(教育コンサルタント)
点数至上主義がもたらす社会的歪み
この事件が投げかける最も大きな問いは、なぜそこまでして高得点を得る必要があるのか、という点にある。
「企業や教育機関がTOEICのスコアに過度に依存している現状は、健全とは言えません」と人材開発の専門家は警鐘を鳴らす。
「本来、英語力はコミュニケーションツールとしての実用性が重要なはずです。数値化された点数のみを重視する風潮が、このような不正を生み出すのです」
実際、TOEICで高得点を取得しても、実務で英語を使いこなせるとは限らない。にもかかわらず、多くの場面で、TOEICのスコアが英語力の絶対的な指標として扱われている現実がある。
- 依存:TOEICスコアへの過度な依存
- 本質:コミュニケーション力より点数重視
- 歪み:目的と手段の取り違え
- 教育:真の語学学習の軽視
捜査の行方と試験制度改革への展望

広がる捜査の網―組織的関与の解明へ
警察は、王容疑者の供述や押収した電子機器の解析を通じて、背後にある組織の特定を進めている。「報酬を得る約束があった」という供述は、いわゆる「替え玉請負業」の存在を強く示唆している。
「これはいわゆる『闇バイト』の一種である可能性が高い」と犯罪社会学の専門家は分析する。「インターネット上で匿名性を保ちながら、違法な仕事の請負が行われているのです」
捜査は王容疑者個人にとどまらず、同様の不正に関与した可能性のある人物の特定へと広がりを見せている。
試験制度改革と社会の意識変革への期待
この事件を契機に、TOEIC運営団体は試験の厳格化と本人確認の強化を検討しているという。しかし、専門家たちは制度改革だけでなく、社会全体の意識改革が必要だと指摘する。
「TOEICに限らず、資格試験の結果に過度に依存する社会のあり方そのものを見直す必要があるでしょう」と教育学者は語る。「真の英語力とは何か、どのように評価すべきか。企業や教育機関は、独自の評価基準を持つべきです」
また、国際的な試験制度の標準化も課題となっている。「各国の試験制度の違いが、不正行為の抜け道になっている面もあります」と国際教育の専門家は指摘する。
「今回の事件を機に、英語能力の評価方法そのものを根本から見直す良い機会になるかもしれません。スピーキングやライティングなど、実践的なスキルを重視した総合的な評価が求められています」(語学教育研究者)
変わるべき未来の試験制度と社会のあり方

不正行為は許されるものではないが、この事件が投げかけた問題は、一人の留学生の犯罪にとどまらない社会的な課題を含んでいる。
「TOEICのスコアが持つ社会的な価値があまりに高すぎるからこそ、このような不正が発生するのです」と社会学者は分析する。「スコア至上主義から脱却し、真の英語力を多角的に評価する仕組みづくりが必要です」
最終的には、英語能力の評価方法だけでなく、私たちの社会が「能力」や「資格」をどう捉えるかという根本的な問いに立ち返る必要があるのかもしれない。
「点数や資格が目的化する社会では、常に不正の誘惑が生まれます」と教育哲学者は語る。「学ぶこと自体の価値を再認識し、真の国際化とは何かを問い直す時期に来ているのではないでしょうか」
まとめ
- TOEIC試験で中国籍大学院生が替え玉受験で現行犯逮捕
- 昨年から複数回、自分の写真を使い他人名義で900点超を記録
- マスク内に小型マイクを隠し、組織的関与の疑い
- 本人確認の甘さなど試験制度の脆弱性が露呈
- 企業・教育機関のTOEICスコア依存が不正の温床に
- 点数至上主義から脱却し、真の英語力評価への転換が必要