洋菓子や和菓子で知られる全国展開の製菓企業シャトレーゼが、外国人技能実習生に対して長期間にわたり無給での待機を命じていたことが明らかとなりました。
この事案は、労働基準法に違反する可能性が指摘されており、企業としての社会的責任や、外国人労働者受け入れ制度の構造的な欠陥にも注目が集まっています。
政府機関からは改善命令が下されるという異例の展開となり、企業の姿勢や制度全体の在り方が強く問われています。
本記事では、その経緯や背景、企業の対応と今後の課題までを、丁寧に掘り下げていきます。
外国人労働者を待機させた問題の概要とその背景
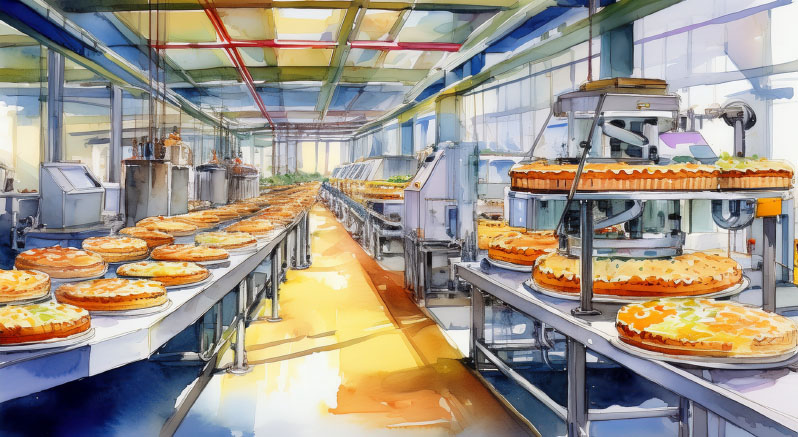
📌POINT:新工場稼働の遅延が発端
シャトレーゼは、新設予定であった三つの工場の稼働遅れにより、外国人労働者を長期間にわたって待機させました。
シャトレーゼは、山形県、岡山県、鹿児島県に新設する工場の準備に伴い、山梨県内の既存工場における人手不足を補う目的で、ベトナム人労働者88人と雇用契約を締結しました。
彼らは「特定技能」という在留資格を持ち、日本国内での就労が法的に認められていた存在です。
ところが、新工場の建設や稼働が予定よりも大幅に遅延したことから、シャトレーゼは該当する外国人労働者たちに対し、約2か月半にわたり就業せずに待機するよう指示したと報じられています。
しかも、この待機期間中には、生活を支える休業手当が一切支払われていなかったことが問題視されているのです。
 外国人労働者
外国人労働者待機中は生活費に困りました。何の説明もなかったです
労働基準法と民法に照らして見る企業の法的責任


労働者が会社都合で仕事を休まされる場合、平均賃金の60パーセント以上を支払う義務が企業に課せられています。
労働基準法第26条では、使用者の都合により労働者が業務に従事できなかった場合には、休業手当として平均賃金の60パーセント以上を支給することが義務づけられています。
これは、企業の事情により労働の機会が奪われた場合でも、最低限の生活を保障するための法律です。
さらに、民法第536条第2項でも、債権者の責めに帰すべき事由によって契約が履行できない場合には、相手方に報酬の支払い義務が残るという規定があります。
これらの条文を踏まえると、今回のシャトレーゼの対応は、明確に法令違反と判断される可能性が高く、企業としての法的・倫理的責任が問われる事案であると言えるでしょう。
シャトレーゼの対応と再発防止への取り組み


シャトレーゼ側は、今回の事案に関し、当初は「給与の支払い先口座の情報収集が完了していなかったため、支給ができなかった」と説明し、事務手続きの不備が原因であるとしました。
しかしこの説明では、労働者への対応の誠実さや制度的な準備不足が露呈しており、社会的な批判を強く受けることになりました。
シャトレーゼは未払い分の支払いはすでに済ませたとしています。
さらに、再発防止に向けて、外部の有識者を招いた調査委員会を設置するなどの対応に乗り出しています。
「多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。再発防止に向け、真摯に取り組んでまいります」
企業コメント
出入国在留管理庁の動きと制度の今後の課題


出入国在留管理庁はこの問題に対して迅速に反応し、シャトレーゼに対して正式な改善命令を発出しました。
その内容は、約1か月以内に状況の是正と具体的な改善内容を記した報告書の提出を義務付けるというものでした。
また、同庁は、今後シャトレーゼが外国人労働者を受け入れる「受け入れ機関」として適格であるかどうかを再評価する姿勢を見せています。
この判断は、今後の同社の雇用方針や事業展開にも大きな影響を与えると見られます。
法務専門家の見解: 「今回の問題は、単なる企業の不手際ではなく、日本の制度全体が抱える本質的な脆弱性を浮き彫りにしています」
まとめ :外国人労働者と制度の信頼性を再確認する必要性
外国人労働者をただの労働力として見るのではなく、人として扱い、尊重する意識改革が必要とされています。
✅今回の事案を通して明らかになった重要なポイント
- シャトレーゼは新工場の稼働遅延を理由に外国人88人に無給待機を命じました
- 労働基準法および民法に違反する可能性が高く、政府機関から改善命令が出されました
- 企業は休業手当の支払いと再発防止策の実行を表明しています
- 出入国在留管理庁は同社の受け入れ機関としての適格性を再審査しています
- 特定技能制度そのものの制度設計や管理体制にも再考が求められています
- 外国人労働者の尊厳を守るため、企業倫理と法令遵守の徹底が必要不可欠です
🌏今後の展望
日本が国際的な労働市場の中で信頼を築くためには、制度と現場の両面から透明性と説明責任を果たす必要があります。企業は収益だけでなく、社会的責任を重く受け止める時代に突入しています。














