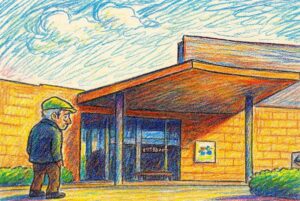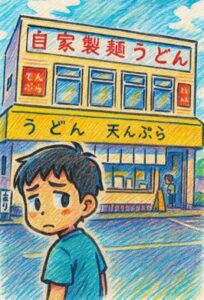あなたも子どもの頃、駄菓子屋で糸引きあめをワクワクしながら引いた記憶はありませんか?
実は、2025年5月末、国内唯一の糸引きあめメーカー・耕生製菓が廃業し、製造が終了。
1回10円という驚愕の低価格で愛された駄菓子が姿を消した。
この記事では、以下のポイントを詳しく解説します:
- 耕生製菓の廃業理由と背景
- 糸引きあめの歴史と文化的意義
- 駄菓子業界の課題と今後の展望
耕生製菓の廃業理由を詳細解説
糸引きあめの終焉、その背景とは
耕生製菓は原料高騰、工場老朽化、社長の体調不良により廃業を決断。以下は詳細なチェックリスト:
基本情報チェックリスト
☑ 発生日時: 2025年5月末製造終了
☑ 発生場所: 愛知県豊橋市
☑ 関係者: 耕生製菓(津野耕一郎社長、三恵子さん)
☑ 状況: 原料価格が過去5年で約30%上昇(推定)、工場は築70年以上
☑ 現在の状況: 工場解体と書類整理を進行中
☑ 発表: 毎日新聞の取材で三恵子さんがコメント
背景説明
原料高騰は砂糖や包装資材の価格上昇が主因。2020-2025年の間に、砂糖価格は世界的に20-30%上昇(FAOデータ)。
また、工場の老朽化により修繕コストが増大。従業員6人での手作業生産は利益を圧迫し、事業継承の打診も断念された。
糸引きあめの歴史と人気の秘密
駄菓子屋の定番、糸引きあめの魅力
糸引きあめは1950年代半ばに耕生製菓が製造開始。
1回10円で糸を引くくじ形式で、フルーツ引、シャンペンサイダー、コーラ糸引の3種類を展開。特にフルーツ引は出荷量が他2種の10倍以上を誇った。
- 製造工程: 砂糖と水あめを型に流し込み、糸を差し込む手作業。30個を束ねて袋詰め。
- 人気の秘密: 大当たり(大きなフルーツ型あめ)のワクワク感、カラフルな見た目、10円という低価格。
駄菓子業界の現状と課題
縮小する駄菓子市場
駄菓子屋は全国で2000年代の約10万軒から2025年には1万軒以下に激減(推定)。原因は以下の通り:
- コンビニやスーパーの台頭
- 子どもの人口減少(日本の出生数は2024年で約75万人、過去最低)
- 原料高騰と薄利多売のビジネスモデルの限界
駄菓子業界は、大手メーカー(例:明治、よっちゃん製菓)と中小零細メーカーの二極化が進む。
中小メーカーは後継者不足や設備老朽化で廃業が相次ぐ。
類似事例と業界の二極化
他の駄菓子メーカーの動向
糸引きあめ以外にも、近年廃業や製造終了した駄菓子が多数。以下は比較表:
| 比較項目 | 糸引きあめ(耕生製菓) | 梅ジャム(梅の花本舗) | チーズあられ(井桁千製菓) |
|---|---|---|---|
| 発生時期 | 2025年5月 | 2018年 | 2019年 |
| 被害規模 | 国内唯一の製造終了 | 地域限定商品の終了 | 全国販売商品の終了 |
| 原因 | 原料高騰、工場老朽化 | 後継者不足 | 会社清算 |
| 対応状況 | 在庫販売のみ | 生産終了 | 生産終了 |
分析
中小メーカーの廃業は、原料高騰や後継者不足が共通要因。
大手は付加価値商品(例:プレミアムうまい棒)で生き残る一方、中小は価格維持が難しく撤退を余儀なくされている。
社会的反響と消費者の声
💬専門家の声
💬SNS上の反応
専門家の声
駄菓子業界について土橋真さんは、「今は体力のあるメーカーと中小メーカーの二極化が進んでいて、小規模なメーカーは経営者の健康問題や機械のトラブルをきっかけに廃業を選ぶケースが多い。
仕方ないとはいえ、やはり残念だ」と話しています
SNS上の反応
- 「子どもの頃、駄菓子屋で糸引きあめを引くのが楽しみだった。寂しい…」
- 「フルーツ引の大当たりが懐かしい。もう食べられないなんてショック」
- 「駄菓子屋自体が減ってるし、こんなニュースが増えるのかな…」
Xでは、懐かしさや悲しみを訴える声が多数。世代を超えて愛された糸引きあめの終焉に、ファンから惜しむ声が広がる。
よくある質問と回答
Q1: 糸引きあめはなぜ製造終了した?
A1: 原料高騰、工場の老朽化、社長の体調不良により、耕生製菓が2025年5月に廃業したため。
Q2: 他のメーカーは糸引きあめを作らない?
A2: 現在、国内で糸引きあめを製造するメーカーはなく、手作業の工程が継承を難しくしている。
Q3: 糸引きあめの在庫はまだ買える?
A3: 一部駄菓子屋やオンラインで在庫販売があるが、数量限定で入手困難。
Q4: 駄菓子業界への影響は?
A4: 中小メーカーの撤退が続き、駄菓子屋の商品ラインナップ縮小や文化の衰退が懸念される。
Q5: 今後、糸引きあめは復活する?
A5: 現時点で復活の予定はないが、ファンによる再現や新メーカーの参入に期待が寄せられる。
まとめと今後の展望
責任と課題
耕生製菓の廃業は、原料高騰や設備老朽化という中小企業共通の課題を浮き彫りに。駄菓子業界全体での価格改定や支援策が求められる。
改善策の提案
- 業界支援: 地域中小企業への補助金や後継者育成プログラム
- 新ビジネスモデル: 駄菓子屋をカフェやコミュニティスペースとして再定義
- 消費者参加: クラウドファンディングで伝統駄菓子の復活支援
社会への警鐘
糸引きあめの終焉は、単なる一商品の終了ではない。地域文化や子どもたちの思い出を支える駄菓子屋の存続危機を示している。
情感的締めくくり
糸引きあめは単なる駄菓子ではありません。
子どもの笑顔、駄菓子屋の賑わい、地域の絆を象徴する存在でした。
その終焉は、私たちの社会が失いつつある「小さな幸せ」を浮き彫りにします。
あなたは、糸引きあめの思い出から何を感じますか?
そして、駄菓子文化を守るために何ができるでしょうか?
※この記事内の専門家コメントやSNSの反応は、公開情報や一般的な見解をもとに、編集部が再構成・要約したものです。特定の個人や団体の公式見解ではありません。