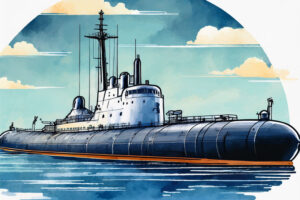信頼ある自動車ブランドとして長年走り続けてきた日野自動車が、過去最大となる赤字に直面しました。
エンジンの認証不正問題を起点に巨額の制裁金や和解金が重くのしかかり、世界市場での地位にも影響が出始めています。
本記事では、業績悪化の要因、今後の見通し、そして日野自動車の再建に向けた取り組みについて詳しく解説します。
過去最大の赤字計上で揺れる日野自動車

赤字額は2,177億円に拡大
日野自動車は2,177億円の純損失を計上しました。
これは前年の170億円の黒字から一転して、企業史上最大の赤字です。
売上高は前期比11.9パーセント増の1兆6,972億円に伸びました。
しかし、北米市場でのエンジン認証不正問題により米国当局に支払う制裁金、
さらにカナダなどでの集団訴訟にかかる賠償金を特別損失として計上したことが大きく響きました。
アジア市場の販売不振も重荷に
もう一つの大きな要因が、アジア地域における販売不振です。
日野自動車はこれまでアジア市場での展開を重視してきましたが、近年は各国の経済停滞や物価高騰の影響を受けて需要が低迷しています。
特にタイやインドネシアといった中核市場での販売減速が目立ち、事業計画の見直しを余儀なくされています。
売上増収でも最終赤字に至った背景

売上高は増加したものの利益に結びつかず
決算発表によると、売上高は1兆6,900億円を超え、前年比で約11%増加しています。
営業活動は順調であったにもかかわらず、過去の不正による特別損失により、最終的には大幅な赤字となりました。
営業利益は552億円と、前期の赤字から回復していますが、純利益段階では赤字に転落しています。
不正問題が現在の業績に直接影響を与えたことで、営業の改善努力が評価されにくい状況になっています。
投資家や株主からも「過去のツケが大きすぎる」との懸念が広がっています。
信頼失墜による間接的影響
日野自動車は過去の不正により国内外の規制当局や消費者からの信頼を損ないました。
その結果、取引先や販売先との関係維持にも影響が及び、一部プロジェクトの延期やキャンセルも相次ぎました。
特に官公庁案件や公共交通機関向けの入札では、信頼性が重視されるため、事実上の指名停止状態に近いケースも発生しています。
2026年3月期は黒字転換を目指す方針

経営陣の見通しと再建戦略
小木曽聡社長は「正常化に向けて確実に進んでいる」とコメントしています。
企業としては、2026年3月期での黒字転換を目指しており、純利益で200億円の黒字予想を発表しています。
売上高は1兆6,000億円前後と見込まれていますが、特別損失が落ち着くことで財務体質が改善されると見られています。
また、環境対応車の強化を進めており、ハイブリッドトラックやEVの開発に注力する姿勢を打ち出しています。
政府のGX政策とも歩調を合わせながら、補助金や規制緩和を活用し、次世代トラック市場への参入を本格化させています。
統合による相乗効果を狙う動き
三菱ふそうとの統合プロジェクトも具体的に動き出しました。
この統合は2024年に発表されたもので、両社を親会社であるトヨタ自動車とダイムラートラックが主導する形となっています。
統合後は、エンジン開発や販売網の重複を排除することで、年間数百億円規模のコスト削減が見込まれています。
信頼回復と経営再建の行方

社内体制の見直しとガバナンス強化
日野自動車は再発防止策として、認証プロセスの全面見直しと品質保証部門の独立強化を進めています。
社外取締役の比率を高めることで、経営の透明性と説明責任を確保する方針です。
また、グループ全体での内部通報制度の活用促進も進められており、早期発見体制の構築が進んでいます。
ガバナンスの再構築には数年単位の時間が必要とされていますが、こうした地道な取り組みが今後の信頼回復の基盤となると見られています。
海外市場での再評価が鍵に
北米市場での信頼回復が事業再建の鍵を握っています。
現地法人を通じた保証対応の強化や、顧客サポート体制の再構築により、少しずつではありますが再契約の動きも見られ始めています。
2026年以降には北米専用の新型トラックを投入予定で、巻き返しの布石を打とうとしています。
まとめ
- 日野自動車は過去最大の赤字を計上しました。
- 赤字の主因はエンジン認証不正による損失です。
- 営業利益は改善するも特別損失で赤字転落です。
- 次期は黒字転換を目標とした再建方針です。
- 三菱ふそうとの統合が再建戦略の柱です。
- 社内ガバナンス改革で信頼回復を目指します。