キユーピーは2025年6月12日、1960年から続く育児食(ベビーフード・幼児食)事業を2026年8月末で終了すると発表した。
原材料価格の高騰や販売数量の低迷により事業継続が困難と判断。全72品目が順次販売終了となり、65年の歴史に幕を下ろす。
関連記事
- キユーピー育児食の生産終了時期と対象商品
- 事業撤退に至った3つの主要因
- 今後1年間の移行期間の対応策
- 子育て世帯への影響と代替品選びのポイント
概要テーブル
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発表日 | 2025年6月12日 |
| 生産終了時期 | 2026年8月末 |
| 対象商品数 | 全72品目(瓶詰21品、カップ容器20品など) |
| 事業継続年数 | 65年(1960年~2026年) |
| 撤退理由 | 販売数量低迷、原材料・エネルギー費高騰 |
| 移行期間 | 約1年間(段階的な在庫調整) |
| 今後の方針 | 子どもの食と健康に貢献する活動は継続 |
事実関係の整理

キユーピーが2025年6月12日に発表した育児食事業からの全面撤退は、日本の食品業界に大きな衝撃を与えている。
1960年の事業開始以来、65年間にわたって日本の子育て世帯を支えてきた同社の育児食が、2026年8月末をもって完全に市場から姿を消すことになる。
対象となる全72品目には、世代を超えて愛されてきた瓶詰シリーズをはじめ、近年人気を集めていたレトルトパウチ商品まで、幅広いラインナップが含まれている。
終了対象の全商品カテゴリー
今回の生産終了対象となる72品目の内訳を見ると、瓶詰21品目が最も多く、次いでにこにこボックス(カップ容器)20品目、レンジでチンするハッピーレシピ(レトルトパウチ)14品目と続く。
その他、ベビーデザート6品目、おやつ2品目、やさいとなかよしシリーズのごはん・麺用ソース7品目、スプレッド2品目が含まれる。
同社は急な供給停止による混乱を避けるため、約1年間の移行期間を設定。この期間中は段階的に在庫調整を行いながら、利用者が代替商品を検討できる時間を確保する方針だ。
公式サイトでは各商品の賞味期間も公開し、計画的な購入を促している。
直近の製品終了の動き
実は今回の発表に先立ち、2025年3月にはカップ容器入りベビーフード「すまいるカップ」シリーズ全15品が製造終了している。
当時は終了理由が明確にされず、SNS上では「なぜ急に?」「困る」といった声が相次いでいた。
今回の全面撤退発表により、段階的な事業縮小が進んでいたことが明らかになった。業界関係者は「すまいるカップの終了は、全面撤退への布石だったのではないか」と推測している。
背景・原因分析
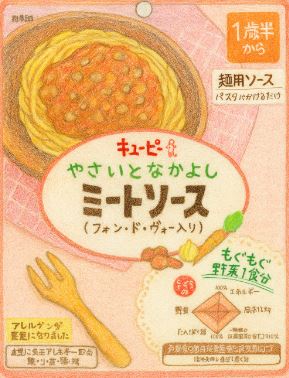
キユーピーが65年続いた育児食事業からの撤退を決断した背景には、複合的かつ構造的な要因が存在している。
同社は公式発表で「近年は自社の販売数量の低迷に加え、原資材価格やエネルギー費の高騰によるコスト増などの厳しい市場環境に直面していた」と説明。
さらに「商品継続のために、設備投資や販売促進を含むあらゆる検討を重ね、立て直しを図ってきたが、お客さまにご満足いただける品質を維持しつつ生産を継続することが困難であると判断した」と苦渋の決断であったことを明かしている。
3つの構造的課題
第一の要因として挙げられるのが、急速に進む少子化による市場規模の縮小だ。厚生労働省の統計によると、2023年の出生数は約75万人と過去最少を更新。
1960年の事業開始当時は160万人を超えていた出生数が、半分以下にまで減少している。この影響でベビーフード市場全体が年々縮小し、各メーカーとも厳しい経営環境に置かれている。
第二の要因は、原材料価格とエネルギーコストの高騰だ。特に2022年以降、ロシアのウクライナ侵攻や歴史的な円安の影響で、小麦や野菜などの原材料費が30~50%上昇。
電気・ガス料金も前年比で20%以上増加し、製造コストが大幅に膨らんでいる。
育児食は一般食品と比べて使用できる原材料が限られ、添加物の使用も制限されるため、コスト削減の選択肢が少ないという特殊事情もある。
第三に、流通構造の変化と競合環境の激化がある。大手小売チェーンのプライベートブランド(PB)商品が台頭し、従来の価格帯での販売が困難になっている。
また、ネット通販の普及により、海外製品も含めた選択肢が広がり、消費者の購買行動が大きく変化している。
品質維持と採算性の両立困難
育児食製造において最も重要なのは、安全性と品質の確保だ。乳幼児が口にする商品であるため、一般食品以上に厳格な品質管理が求められる。
原材料の選定から製造工程、品質検査、アレルギー対応まで、すべての工程で妥協は許されない。
食品製造業に詳しい専門家は「育児食は利益率が低い上に、設備投資や品質管理にかかるコストが高い。
規模の経済が働きにくい商品カテゴリー」と指摘する。
キユーピーも設備の老朽化に直面しており、大規模な設備更新投資が必要な時期を迎えていたが、縮小する市場では投資回収が見込めないという判断に至ったとみられる。
影響・波及効果
キユーピーの育児食事業撤退は、単なる一企業の事業終了にとどまらず、日本社会全体に様々な影響を及ぼすことが予想される。
国内ベビーフード市場で約15%のシェアを占めていた同社の撤退により、約30万世帯の子育て家庭が直接的な影響を受けると推計されている。
特に、アレルギー対応商品や特定の栄養強化商品を利用していた世帯では、代替品探しが喫緊の課題となっている。
さらに、この撤退は少子化対策や子育て支援という国家的課題にも影を落としかねない重大な出来事として受け止められている。
子育て世帯への直接的影響
キユーピーの瓶詰シリーズは、1960年代から続く日本の育児食の代名詞的存在だった。「おかあさんの味」というキャッチフレーズで親しまれ、親子3世代にわたって利用されてきた家庭も少なくない。
東京都在住の30代母親は、私自身も子どもの頃キユーピーの瓶詰で育ち、自分の子どもにも同じものを食べさせていました。
なくなると思うと本当に寂しいし、何より困りますと話す。
特に好き嫌いの多い子どもを持つ親からは、「うちの子はキユーピーの『ももと白ぶどう』しか食べないんです」といった切実な声も上がっている。
アレルギー対応商品を利用していた世帯では、状況はさらに深刻だ。乳・卵・小麦などの特定原材料を使用していない商品は選択肢が限られており、「他社製品で同等の商品を見つけるのが難しい」という声が多い。
小売業界への波及
ドラッグストアやスーパーマーケットなど、育児食を扱う小売店にも大きな影響が及んでいる。
ある大手ドラッグストアチェーンの幹部は「キユーピーは定番中の定番。売場の3分の1を占める店舗もある」と話す。
売場の再編成だけでなく、売上への影響も懸念される。
「キユーピー商品を目当てに来店し、ついでに他の育児用品も購入するお客様が多い。客数減少につながる可能性がある」(小売業界関係者)との指摘もある。
競合他社の動向
キユーピーの撤退により、和光堂(アサヒグループ食品)、ピジョン、森永乳業などの競合他社は市場シェア拡大の機会を得ることになる。すでに各社は生産体制の見直しや、新商品開発を加速させているという。
和光堂は「お客様にご不便をおかけしないよう、商品供給体制を強化する」とコメント。
ピジョンも「当社商品へのスムーズな移行をサポートする体制を整える」と表明している。
しかし、「急激な需要増に対応するのは簡単ではない。しばらくは品薄状態が続く可能性がある」(業界アナリスト)との見方もある。
専門家見解・世論の反応
キユーピーの育児食事業撤退発表は、様々な分野の専門家や一般消費者から多様な反応を引き出している。
栄養学の専門家からは商品の質の高さを惜しむ声が上がる一方、経営学の観点からは「やむを得ない判断」との見解も示されている。
SNS上では撤退を惜しむ声が圧倒的多数を占め、中には幼少期の思い出とともに商品への愛着を語る投稿も多く見られた。
この撤退が日本の少子化対策にも影響を与えかねないとの懸念も、各方面から指摘されている。
栄養学専門家の視点
管理栄養士で乳幼児の食事指導を専門とする田中美智子氏(仮名)は、「キユーピーの育児食は、栄養バランスと美味しさを高いレベルで両立していた」と評価する。
特に野菜嫌いの子どもでも抵抗なく食べられる工夫や、月齢に応じた固さ・大きさの調整が秀逸だったという。
最近は離乳食の手作りを推奨する風潮もありますが、忙しい現代の親にとって市販品は重要な選択肢。
質の高い商品が市場から消えることは、子育て支援の観点からもマイナスと懸念を示す。
一方で、近年は消費者ニーズが多様化し、オーガニックや無添加、地産地消など、様々な価値観が生まれている。
大量生産型の商品では対応しきれない面もあったと市場変化についても言及している。
SNSでの反応
X(旧Twitter)では発表直後から「#キユーピー育児食」がトレンド入りし、24時間で10万件を超える投稿が確認された。
「息子が唯一完食する瓶詰がなくなるなんて」「3世代でお世話になりました」といった惜しむ声が大半を占めた。
中には「私が赤ちゃんの時の写真に写っているキユーピーの瓶。同じものを我が子にも食べさせたかった」という世代を超えた思い出を語る投稿も。
一方で、「正直高かった」「PB商品で十分」という価格面での課題を指摘する声も一部で見られた。
少子化対策への影響懸念
児童福祉政策に詳しい大学教授は、「政府は異次元の少子化対策を掲げているが、民間企業が育児関連事業から撤退する流れは、その政策効果を減殺しかねない」と警鐘を鳴らす。
「育児の負担軽減は少子化対策の重要な柱。選択肢が減ることで、子育てのハードルが上がる可能性がある。
公的支援だけでなく、民間企業が育児関連事業を継続できる環境整備も必要」と指摘。具体的には、育児食製造に対する補助金や税制優遇措置などの検討を提案している。
今後の展開・見通し
キユーピーは2026年8月の生産終了まで約1年間の移行期間を設けているが、この期間をどう活用するかが、子育て世帯や小売業界にとって重要な課題となっている。
同社は「急な供給停止によるお客さまやお得意先の皆さまへのご負担を最小限にとどめる」としており、段階的な在庫調整を行いながら、市場の混乱を避ける方針だ。
一方で、消費者や小売店側も、この1年間で新たな商品選択や売場構成を模索する必要がある。
さらに、キユーピーが蓄積してきた65年分のノウハウをどう活かしていくかも、業界全体の課題として浮上している。
1年間の移行期間の活用法
キユーピーは移行期間中、人気商品を中心に生産を継続し、段階的に品目数を減らしていく計画だ。
小売店向けには、在庫状況や終売時期の情報を定期的に提供し、売場の混乱を最小限に抑える。
消費者に対しては、公式サイトで各商品の賞味期限情報を公開し、計画的な購入を促している。
「お子様の成長に合わせて、早めに代替商品をお試しいただくことをお勧めします」(同社広報)
大手小売チェーンでは、すでに対応を開始。「キユーピー商品の在庫を確保しつつ、他社商品の品揃えを段階的に拡充していく」(大手スーパー幹部)方針だ。
代替商品選びのポイント
小児科医で離乳食指導も行う医師は、代替商品を選ぶ際のポイントとして以下を挙げる。
「まず原材料表示を確認し、アレルギー物質の有無をチェック。次に、月齢に適した固さや大きさか、栄養成分は十分かを見る。最後に、実際に少量購入して子どもの反応を確認することが大切」
特に、今までキユーピー商品に慣れ親しんだ子どもの場合、味や食感の違いで急に食べなくなることもある。
「焦らず、複数の商品を試しながら、お子様に合うものを見つけてください」とアドバイスしている。
キユーピーの新たな取り組み
同社は育児食の生産・販売は終了するものの、「これまで培ってきた『品質』への姿勢を継承し、子どもたちの食と健康に貢献する活動は継続する」と表明している。
具体的には、食育プログラムの提供や、アレルギーに関する情報発信、レシピ開発支援などが検討されているという。
また、業界関係者の間では「65年間蓄積したレシピや製造ノウハウを、何らかの形で業界に還元する可能性もある」との観測も出ている。
「完全に失われるのはもったいない。技術提携やライセンス供与など、様々な選択肢があるはず」(食品コンサルタント)
FAQ
Q1: なぜ1年も前に発表したのですか?
A: 急な販売終了による混乱を避け、利用者が代替商品を検討する時間を確保するためです。特にアレルギー対応商品を利用している方には、十分な準備期間が必要と判断しました。
Q2: 在庫がなくなる前に買いだめした方がいいですか?
A: 賞味期限を考慮した適量の購入をお勧めします。1年間は段階的に供給される予定ですが、人気商品は早めに品薄になる可能性があります。
Q3: キユーピー以外でおすすめの育児食メーカーは?
A: 和光堂、ピジョン、森永乳業などが主要メーカーです。それぞれ特徴が異なるため、お子様の好みや必要な栄養素に合わせて選択することが大切です。
Q4: 手作り離乳食に切り替えるべきでしょうか?
A: 必ずしもその必要はありません。市販品と手作りを組み合わせるなど、ご家庭の事情に合わせた方法を選択してください。無理のない範囲で対応することが重要です。
Q5: キユーピーが撤退したら、育児食の価格は上がりますか?
A: 短期的には需給バランスの変化により、一時的な価格上昇の可能性があります。ただし、中長期的には市場競争により適正価格に落ち着くと予想されます。
まとめ:キユーピー育児食撤退が示す日本の子育て環境の転換点
📊 市場への影響
キユーピー育児食の生産終了により、国内ベビーフード市場の約15%のシェアが他社に移行します。2026年8月末までの移行期間中、約30万世帯が代替商品を探す必要があり、一時的な品薄状態が懸念されています。
65年間の歴史に幕を下ろすキユーピー育児食は、少子化による市場縮小と原材料費高騰という二重の課題を乗り越えられませんでした。
🔍 今すぐ確認すべき3つのポイント
- 愛用商品の在庫状況:人気の瓶詰シリーズは早期品切れの可能性大
- 代替商品の試食期間:お子様に合う商品を見つけるには時間が必要
- アレルギー対応商品:特に選択肢が限られるため早めの対策を
管理栄養士は「代替商品選びは焦らずに」と助言。まず原材料・アレルギー物質・栄養バランス・価格の4点を確認し、少量ずつ試すことを推奨しています。
📈 今後の育児食市場の展望
2026年夏までは需給バランスの崩れから、一時的な価格上昇や品薄状態が予想されます。和光堂、ピジョン、森永乳業など競合他社は増産体制を急ピッチで整備中。
市場再編により、オーガニックやアレルギー対応など専門性の高い商品が増加。一方で、政府の少子化対策と連動した育児食製造支援策の必要性も高まっています。
キユーピー育児食の終了は、単なる一企業の撤退ではなく、日本の子育て環境が大きな転換点を迎えていることを示しています。

