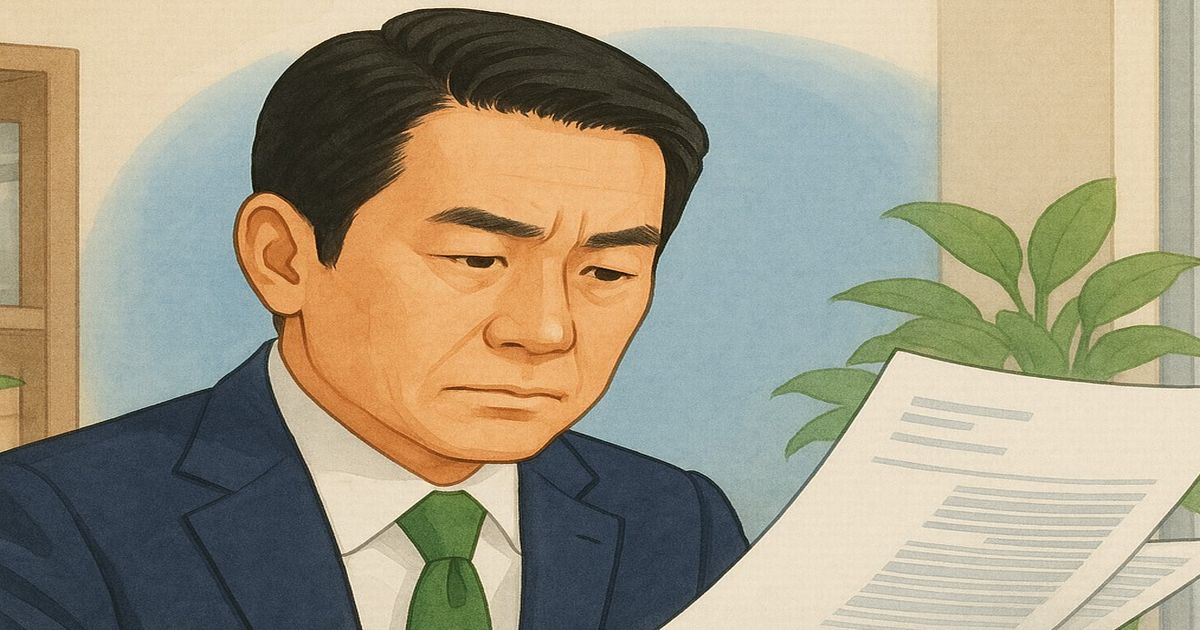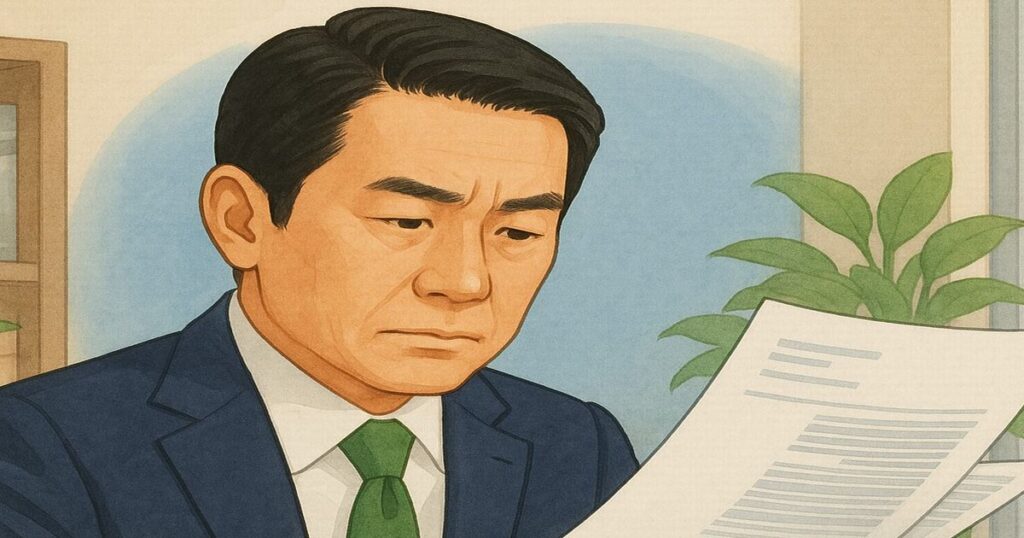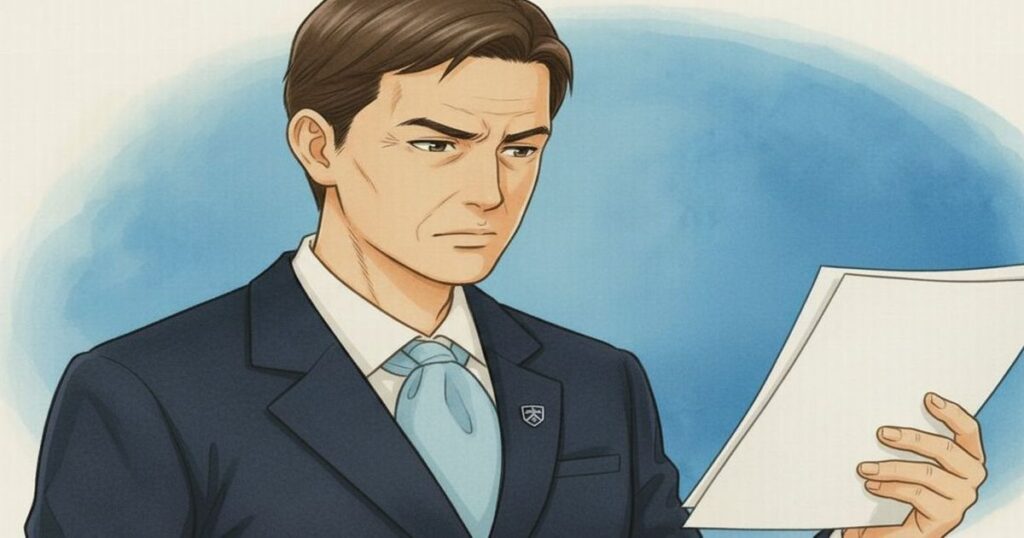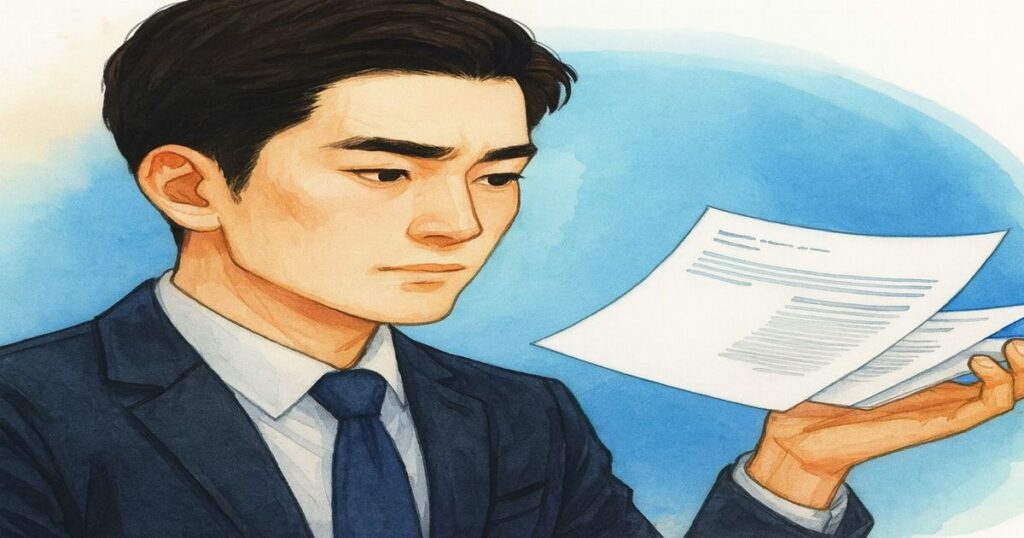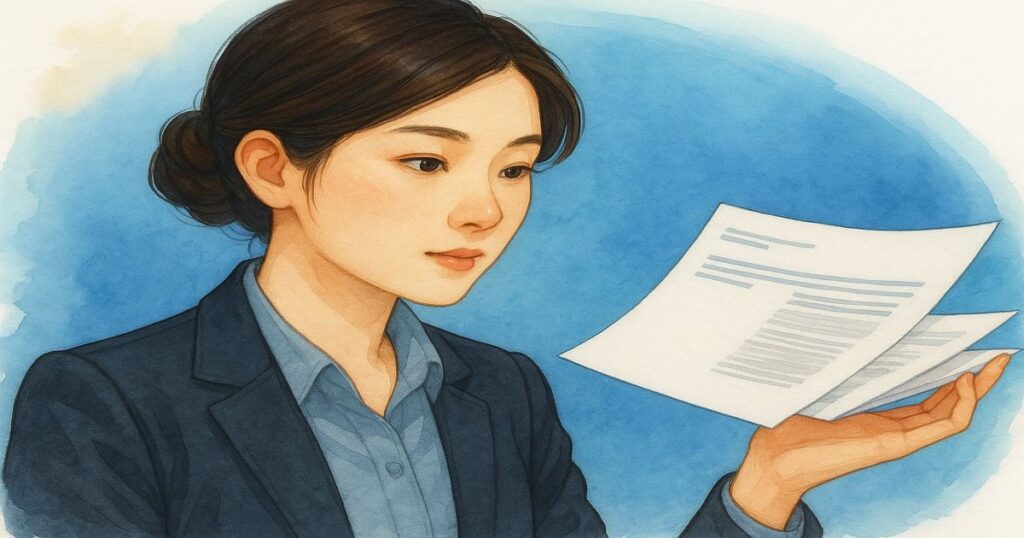富山県高岡市で60年以上にわたり地域の食を支えてきた「高岡総合給食センター」が、2025年10月8日付で富山地裁高岡支部より破産手続き開始決定を受けました。
県内の事業所や福祉施設に給食を届けてきた老舗協同組合が、なぜ経営破綻に追い込まれたのでしょうか。
背景には、物価高や人手不足、そして給食業界特有の構造的課題がありました。この記事では、破産の経緯と今後の地域社会への影響を詳しく解説します。
高岡総合給食センター破産の概要
東京商工リサーチおよび帝国データバンク富山支店の発表によると、協同組合高岡総合給食センター(高岡市美幸町、木田勝也代表理事)は、2025年10月8日付で破産手続き開始決定を受けました。
負債総額は東京商工リサーチによると1億4573万円、帝国データバンクでは約1億6千万円とされています。
1962年の設立以来、県西部地域の事業所・高齢者施設・保育園・幼稚園などに給食を提供し、地域密着型の食のインフラを担ってきました。
物価高と人手不足が経営を圧迫
近年の急激な物価上昇により、食材や燃料費の高騰が続いていました。
さらに、給食業界では調理員や配送ドライバーの人材確保が困難で、人件費の上昇も重なりました。
一方で、契約先である福祉施設や教育機関との長期契約によって価格転嫁が難しく、コスト増を吸収できなかったことが経営悪化の主因とみられます。
また、自治体主導の給食調達において入札競争が激化し、利益率の低下も避けられませんでした。
「地域の食を守る仕組みが必要」
関係者によると、同センターは近年も給食サービスの継続を模索していたものの、資金繰りの限界に達したといいます。
地元自治体の担当者は「長年地域の食を支えてきた協同組合の消滅は痛手。今後は代替供給の確保を急ぐ」とコメントしました。
富山県や高岡市は、利用施設への影響を最小限に抑えるため、他業者との連携支援を進めています。
給食インフラの継続に暗雲も
高岡総合給食センターの破産は、地方都市の給食インフラの脆弱性を浮き彫りにしました。
全国的にも同様の中小給食事業者の経営難が続いており、今後も物価上昇やエネルギーコスト高が重荷となる見通しです。
特に高齢者施設では、安定した食事提供体制の再構築が急務とされています。
- 破産手続き開始:2025年10月8日付(富山地裁高岡支部)
- 負債総額:約1億6千万円(帝国データバンク)
- 設立:1962年、県西部の給食供給を担う協同組合
- 原因:物価高、人手不足、価格転嫁困難
- 今後:行政と民間が連携し、代替供給体制を整備
専門家「構造的な課題が表面化」
地域経済アナリストは「給食業界は公共性が高い一方、利益率が非常に低い。原材料費の高騰や人件費増を価格に反映できない仕組みが問題」と指摘します。
また、協同組合型の運営では意思決定の遅れや財務リスクが蓄積しやすく、今後は民間委託や統合化の動きが広がる可能性があります。
SNSでは「寂しい」「お世話になった」の声
地元住民からは「子どもの頃の給食を作ってくれていた」「地域の味がなくなるのは悲しい」といった声が相次いでいます。
一方で、「公共サービスに依存しすぎた構造改革の遅れでは」との冷静な分析も見られました。
地域の食を守る新たな枠組みへ
今回の破産をきっかけに、県内では他の協同組合や民間給食会社が協議の場を設け、共同仕入れや配送の合理化を検討中です。
行政も地産地消の推進や中小給食事業者のデジタル化支援を強化しており、「地域一体の食インフラ再建」が次の焦点となっています。
- Q1. 高岡総合給食センターの設立はいつ?
A. 1962年に協同組合として設立され、約60年にわたり地域給食を提供していました。 - Q2. 負債額はいくら?
A. 東京商工リサーチで1億4573万円、帝国データバンクでは約1億6千万円とされています。 - Q3. 利用施設への影響は?
A. 高齢者施設や保育園への供給停止リスクがあり、行政が代替業者との調整を進めています。 - Q4. 今後の再建策は?
A. 行政支援のもと、共同配送やデジタル化によるコスト削減を目指す動きがあります。
高岡総合給食センターの破産は、地方における給食インフラの危機を象徴しています。
経済的な厳しさのなかで、地域の「食の公共性」をどう守るかが問われています。
官民連携による新たな枠組みづくりが急務です。