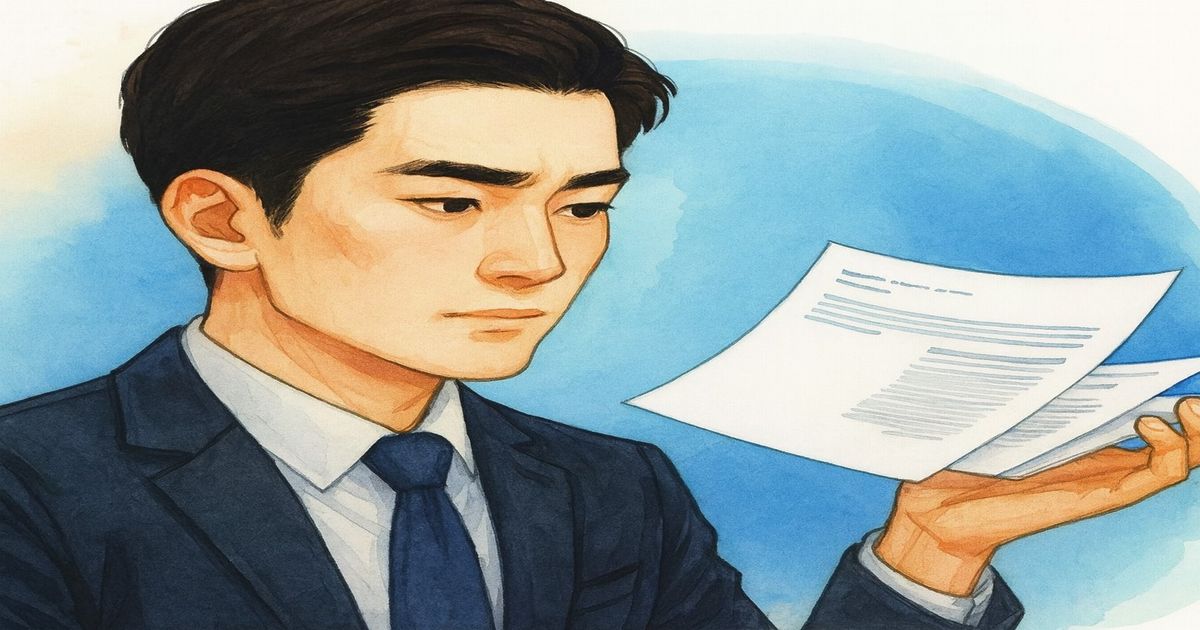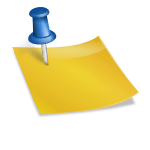長年にわたり登山やキャンプ愛好者に親しまれてきた大分市の老舗アウトドア専門店「山渓」が破産手続き開始の決定を受けました。
実店舗ならではの専門知識と商品ラインナップで支持されてきた同店ですが、経営環境の悪化により自己破産に追い込まれました。
本記事では、山渓の歴史や破産の詳細、そして今後のアウトドア市場について詳しく解説します。
関連記事
山渓の歴史と役割

大分市の老舗アウトドア専門店である山渓が、破産手続き開始の決定を受けました。
山渓は1968年に創業し、九州地区で登山やアウトドア用品を専門に取り扱う店舗として長年親しまれてきました。
地元の登山愛好者やアウトドアファンにとっては、信頼できる専門店として確固たる地位を築いていました。
破産手続きの詳細
山渓は3月24日に大分地方裁判所へ自己破産を申請し、26日には破産手続き開始の決定を受けました。
負債総額は約3億2300万円に上るとみられています。長年親しまれてきた老舗店舗の破綻は、多くの顧客にとっても大きな衝撃となりました。
コロナ禍による影響
コロナ禍によりアウトドアレジャーの人気が急上昇し、2021年9月期には年間約16億円もの売上を記録しました。
しかし、その後の市場環境の変化が大きな打撃となりました。
オンライン市場の台頭

特に、オンライン市場の拡大による価格競争の激化が経営に深刻な影響を及ぼしました。
大手ECサイトや海外通販サイトの影響で、実店舗での販売が次第に難しくなり、価格競争に巻き込まれた結果、利益の確保が困難になりました。
コストの上昇
加えて、原材料の高騰や輸送コストの上昇など、業界全体のコスト増加も経営に大きな負担を与えました。
特に登山用品やキャンプ用品の仕入れ価格が上昇したことで、利益率が低下し、資金繰りが厳しくなりました。
消費者の購買意欲の低下
物価上昇による消費者の購買意欲の低下も影響しました。高額なアウトドア用品の購入を控える動きが広がり、売上が次第に減少していきました。
実店舗の競争力低下

さらに、都市部を中心に新たなアウトドア専門店の進出が相次ぎ、競争が激化しました。
特に全国展開する大型アウトドアショップやスポーツ用品チェーン店が充実した品揃えと低価格戦略を打ち出したことで、中小規模の専門店が苦境に立たされる状況となりました。
今回の破産が示すもの
この事例は、オンライン市場の拡大がリアル店舗の経営にどのような影響を与えるかを示す象徴的な出来事です。
インターネットの普及により、消費者は手軽に低価格の商品を購入できるようになりましたが、一方で実店舗ならではのサービスや専門性を求める声も根強くあります。
特に登山用品やキャンプ用品は、使用目的に合わせた適切なアドバイスが求められる商品が多く、実店舗での接客やアフターサポートが重要視される分野です。
しかし、価格競争が優先される市場環境では、そうした付加価値を提供する実店舗の維持が難しくなっています。
アウトドア市場の今後

今後、アウトドア用品市場がどのように変化していくのか、そしてリアル店舗がどのように生き残りを図るのかが注目されます。
消費者のニーズが変化する中で、実店舗ならではの価値をどのように提供していくのかが課題となるでしょう。
特に、リアル店舗の強みを生かしたサービスの充実や、ECサイトとの連携によるハイブリッド型の販売戦略が求められる可能性があります。
また、地域密着型の経営を進めることで、大手との差別化を図ることも重要になるでしょう。
まとめ
- 山渓は3月24日に自己破産を申請しました。
- 負債総額は約3億2300万円に上ります。
- 原材料の高騰や消費者の購買意欲低下も要因です。
- コロナ禍で一時は売上が増加しました。しかし、オンライン市場の競争激化が影響しました。
実店舗の価値提供には、地域密着型戦略が重要です。また、アウトドア市場の変化を見極めた柔軟な経営が求められます。